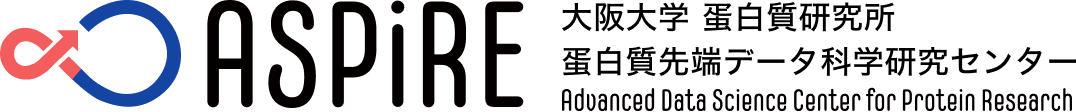Researcher
古賀 信康 センター長
Nobuyasu Koga
- 所属:
- 大阪大学 蛋白質研究所 蛋白質デザイン研究室 教授
- 研究内容:
- 計算機および生化学実験を用いてタンパク質デザインすることで、タンパク質の構造形成及び機能発現のメカニズムを理解し、望みのタンパク質を創出する手法を開発する。
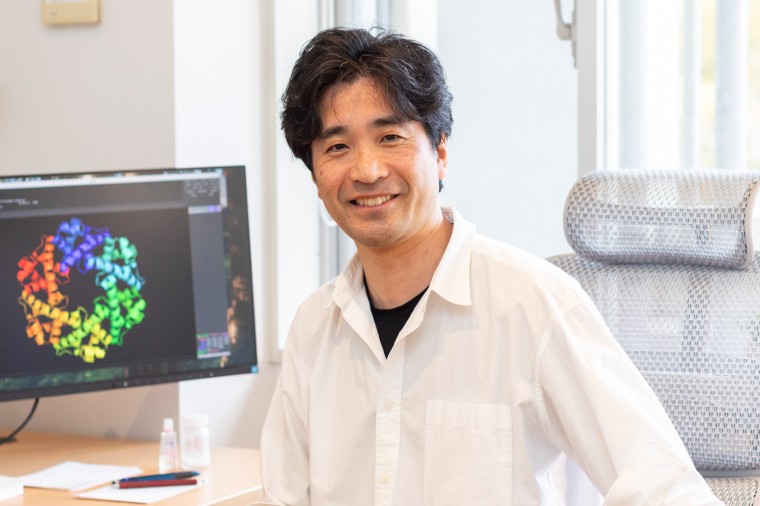
研究紹介
タンパク質分子は、20種類のアミノ酸が1次元的につながった鎖状の高分子であり、各アミノ酸配列に基づいて固有の立体構造へと折りたたみ、その立体構造をもとに機能を発現します。アミノ酸配列の組み合わせは、N残基のタンパク質の場合で20^N通りと膨大であり、例えば100残基のタンパク質では約10130通りにも及びます。この広大な配列空間には、生物が進化の過程で生み出したタンパク質以外に、医療、産業、細胞の制御設計に役立つ新規タンパク質が多く存在すると考えられています。私達は自然界のタンパク質データ、AI、分子シミュレーションを用いることで新規タンパク質を計算機上で生成し、生成したタンパク質について生化学実験を行うことで、タンパク質分子の構造形成と機能発現の仕組みを理解し、タンパク質をゼロからデザインする手法の開発を目指しています。
もっとくわしくQ&A

この研究のユニークな点や強みを教えてください。
計算機を使ったデザインと、生化学の実験の両方を組み合わせて研究を進めるところです。計算機で設計したタンパク質は、あくまで仮想のものなので、本当にその通りの形や機能を持つかどうかは、実験で確かめないとわかりません。研究では、まず計算機を使ってタンパク質、つまりアミノ酸配列を設計します。次に、その配列をコードした遺伝子を大腸菌に組み込みます。大腸菌に設計したタンパク質を作らせて、それを取り出し、狙った通りの構造や機能を持っているかを確認します。自分で設計したタンパク質が思い通りの形になって、期待通りの機能を持っていたときの嬉しさは、他に比較するものが、なかなか無いのではと思っています。
この研究に、データサイエンスがどのように関わるのか教えて下さい。
タンパク質の機能は、タンパク質が形成する立体構造で決まっています。1960年にミオグロビンと呼ばれるタンパク質の立体構造が決定(Link: https://numon.pdbj.org/mom/1?l=ja)されて以降、これまでに様々なタンパク質の立体構造が決められ、その構造データが集積されています (Link to PDBj: https://pdbj.org)。タンパク質の立体構造は2重螺旋構造を持つDNAと異なり、一目では規則性や対称性を見つけることがむずかしい複雑な形をしています。私達の研究では、これまでに実験的に得られた自然界にあるタンパク質の立体構造データをもとに、これらを解析、学習することや、分子シミュレーションを行うことで、自然界に無いタンパク質を創出することを目指しています。
関連する研究およびプロジェクト
主な論文、書籍
論文
- T. Kosugi, M. Tanabe, N. Koga, De novo design of ATPase based on a blueprint optimized for harboring the P-loop motif, Protein Science, 34(6): e70132 (2025).
https://doi.org/10.1002/pro.70132 - T. Matsuzaki, T. Saeki, F. Yamazaki, N. Koyama, T. Okubo, D. Hombe, Y. Ogura, Y. Hashino, R. Tatsumi-Koga, N. Koga, R. Iino, A. Nakamura, Development and Production of Moderate-Thermophilic PET Hydrolase for PET Bottle and Fiber Recycling, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 13(27), 10404-10417 (2025).
https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c01602 - K. Sakuma, N. Kobayashi, T. Sugiki, T. Nagashima, T. Fujiwara, K. Suzuki, N. Kobayashi, T. Murata, T. Kosugi, R. Tatsumi-Koga, N. Koga, Design of complicated all-α protein structures, Nature Structural & Molecular Biology, 31, 275-282 (2024).
https://doi.org/10.1038/s41594-023-01147-9 - S. Minami, N. Kobayashi, T. Sugiki, T. Nagashima, T. Fujiwara, R. Tatsumi-Koga, G. Chikenji, N. Koga, Exploration of novel αβ-protein folds through de novo design, Nature Structural & Molecular Biology, 30, 1132-1140 (2023).
https://doi.org/10.1038/s41594-023-01029-0 - R. Koga, N. Koga, Consistency principle for protein design, Biophysics and Physicobiology, 16, 304-309 (2019).
https://doi.org/10.2142/biophysico.16.0_304
書籍
- 古賀信康, 巽理恵, 物理科学と経験的ルールに基づく de novo デザイン, 実験医学, 43(15)増刊号, 2431-2436 (2025).
- 古賀信康, 巽理恵, 2024年ノーベル賞解説 化学賞 計算によるタンパク質の設計 自然界に存在しない構造と機能, 化学, 79(12) 24-26 (2024).
- 古賀信康, 2024年ノーベル賞解説レビュー 3 化学賞 自然が未踏のタンパク質をゼロから創り出す, 実験医学, 42(19), 3017-3018 (2024).
- 古賀信康, 巽理恵, 2024年ノーベル賞 2024年ノーベル化学賞 計算によるタンパク質の設計と構造予測, 現代化学, 645, 17-20 (2024).
- 古賀理恵, 小杉貴洋, 古賀信康, タンパク質の新常識 4. De novo デザインタンパク質-生物がもたないタンパク質を設計できる時代, 実験医学, 40(12), 2046-2054 (2022).