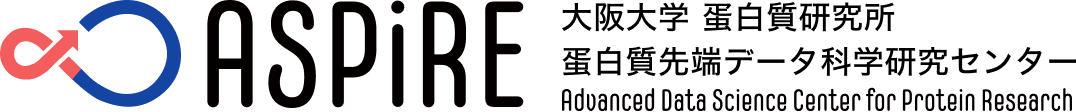Researcher
水口賢司
Kenji Mizuguchi
- 所属:
- 大阪大学 蛋白質研究所 計算生物学研究室 教授
創薬インフォマティクス研究室 教授(兼任) - 研究内容:
- ゲノム・タンパク質から化合物に至る幅広いデータに人工知能や機械学習などのコンピュータ技術を適用することで、創薬や健康研究の進展を目指す
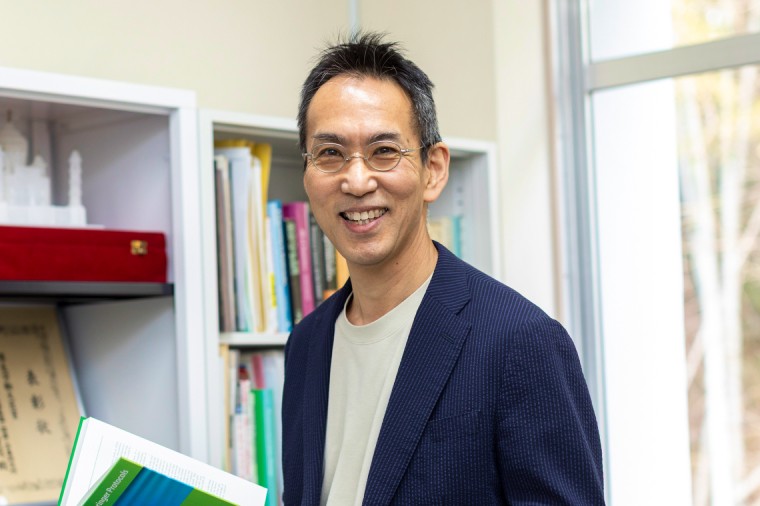
研究紹介
分子レベルと高次の生命現象をつなげるための基盤となる幅広いデータの統合やデータベース開発を行いながら、蛋白質の構造、機能、相互作用などを予測する手法の開発を行っています。また、これらのデータベースや解析ツールを用いて、具体的な生命科学データ解析や健康・創薬研究への応用も推進しています。
もっとくわしくQ&A
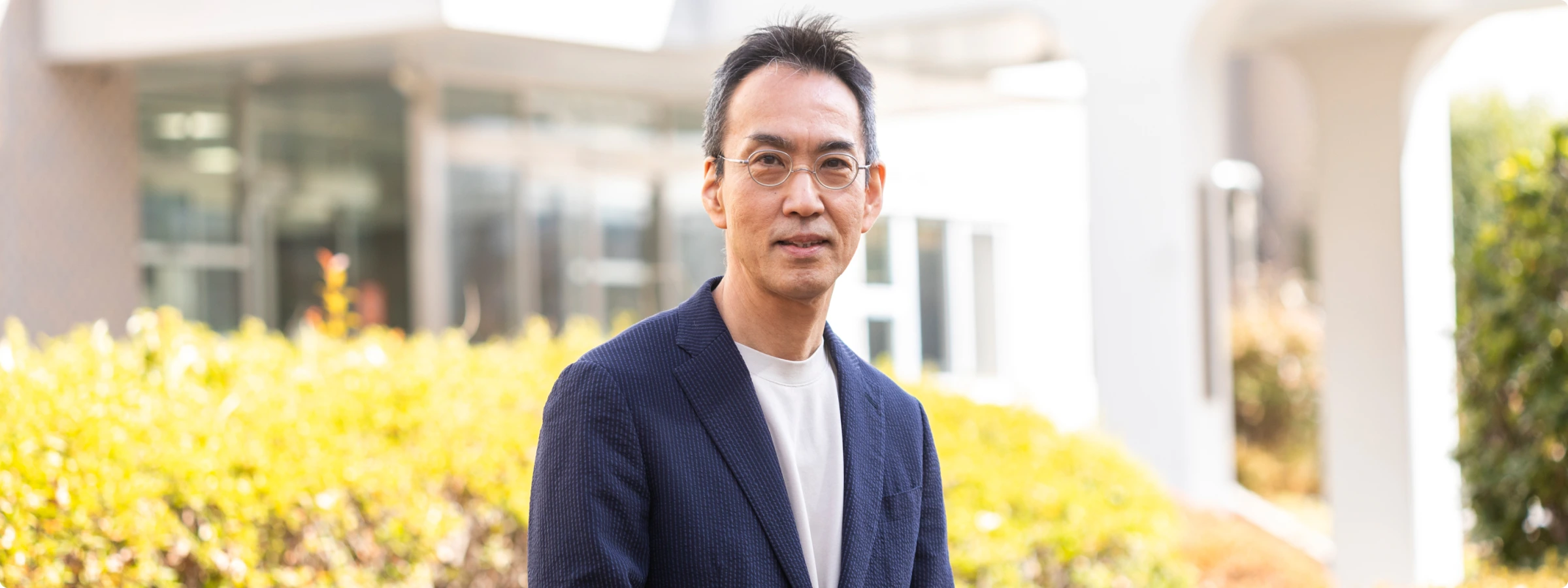
この研究のユニークな点や強みを教えてください。
機械学習・人工知能(AI)を用いたモデリングや予測は、タンパク質の立体構造など、質の整った大規模なデータが利用可能な場合に大きな成功を収めています。一方、創薬応用を含む生物学の分野では、データが散在しているあるいは質の担保が十分でないなどの理由から、AIの活用が困難な事例が多くあります。我々の研究は、独自のデータ統合技術を用いたデータベース開発や効率的なキュレーションシステム構築などデータに中心を置いたAI基盤の構築に貢献していること、またナノ粒子、核酸医薬から医薬品候補の薬物動態まで幅広い問題についての予測モデル開発を行なっている点が、他にない強みだと考えています。
この研究の成果は、社会や産業にどのように役立つと考えていますか?
新しい薬を生み出すのに莫大な費用と時間がかかる理由の一つに、細胞や動物を用いた実験で見出された医薬品候補が、必ずしもヒトでの薬効に結びつかないという大きな問題があります。人間で直接実験はできないので、何らかの間接的な情報を用いて体内で起こっている現象の理解を深める試みは必須です。その際に、幅広い種類の生命情報を統合しモデル化するというアプローチが重要な役割を果たします。我々の薬物動態や腸内細菌叢・生活習慣データベースと予測技術は、薬によって病態を制御するのみならず、個人差に応じた健康の維持など、より幅広い意味での健康社会の実現に貢献できると考えています。
この研究では、データサイエンスがどのように活用されていますか?
対象の問題に応じて適切にデータを取得・統合して質の高い学習データセットを作成するキュレーションと呼ばれる作業、得られたデータについての可視化やパターンの分析、深層学習を含む各種機械学習アルゴリズムを用いた予測モデルの構築、研究成果であるデータベースやプログラムをウェブアプリケーションとして公開するためのソフトウェア開発など、我々の研究のほとんど全てにデータサイエンスの技術が活用されています。
共同研究の事例や今後のコラボレーションの可能性について教えてください。
複数の製薬企業や技術系企業との共同研究により、タンパク質設計や医薬品開発の効率化を目指した新たな手法開発を行っています。またこれまでに、製薬企業コンソーシアムを作ってデータ共有の枠組みを構築したり、我々が開発したソフトウェアやデータベースをIT系企業にライセンスアウトして商用化することで、研究成果の社会実装も行なってきました。今後も、新規創薬標的の探索を目指した企業などとの共同研究から、生命現象や疾患のメカニズム解明を目指したより基盤的なアカデミア研究まで、幅広いコラボレーションを展開してきたいと考えています。
今後の研究の展望や目標を教えてください。
コンピュータ解析あるいはAIフレンドリーな形でデータを集積し、共有するにはどうしたらよいか、データ生産者が進んでデータを提供してくれる枠組みをどう作るのか、という問いに、技術的な観点から貢献できればと考えています。また、タンパク質など分子レベルの解析と、細胞や個体といった高次の生命現象とを結びつけるためには、まだ多くの困難を乗り越えねばいけないのが現状です。多様な生命情報の統合という切り口からこの問題にアプローチし、例えば薬物代謝酵素における分子レベルのモデリングから医薬品応答に対する個人差までをつなげるといった、具体的な現象に迫っていきたいと考えています。
主な論文、書籍
論文
- Wang et al., Biological age prediction using a DNN model based on pathways of steroidogenesis, Science Advances, in press (2024).
https://doi.org/10.1126/sciadv.adt2624 - K. Koyama, K. Hashimoto, C. Nagao and K. Mizuguchi, Attention network for predicting T-cell receptor–peptide binding can associate attention with interpretable protein structural properties, Front. Bioinform., 3, 1274599 (2023).
https://doi.org/10.3389/fbinf.2023.1274599 - H. Kawashima, R. Watanabe, T. Esaki, M. Kuroda, C. Nagao, Y. Natsume-Kitatani, R. Ohashi, H. Komura and K. Mizuguchi, DruMAP: A novel drug metabolism and pharmacokinetics analysis platform, J. Med. Chem., 66(14), 9697-9709 (2023).
https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.3c00481 - R. Watanabe, K. Hashimoto, K. Higashisaka, Y. Haga, Y. Tsutsumi and K. Mizuguchi, Evidence-based prediction of cellular toxicity for amorphous silica nanoparticles, ACS Nano, 17(11), 9987-9999 (2023).
https://doi.org/10.1021/acsnano.2c11968 - Y.-A. Chen, R. S. Allendes Osorio and K. Mizuguchi, TargetMine 2022: a new vision into drug target analysis, Bioinformatics, 38(18), 4454–4456 (2022).
https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btac507