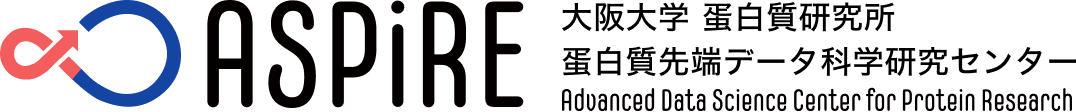ノーベル化学賞にタンパク質デザインと構造予測
- お知らせ
2024年ノーベル化学賞に、デイヴィッド・ベイカー教授(ワシントン大学)、デミス・ハサビスCEO(DeepMind社)、ジョン・ジャンパー氏(DeepMind社)が選ばれました。
受賞、誠におめでとうございます。
ベイカー教授は、特定の構造を形成するアミノ酸配列をデザインするアルゴリズムを、ハサビス氏およびジャンパー氏はアミノ酸配列から立体構造を予測するアルゴリズムを開発しました。
構造予測技術とそのインパクト
タンパク質の立体構造予測は50年の歴史を持つ分野であり、1994年からは2年おきに国際大会 CASP(Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction)が開催されています。
2020年、DeepMind社が開発したAlphaFold2がCASPで圧倒的な精度を記録し、「予測はしょせん予測」という従来の常識を覆しました。これにより、非構造生物学者でもAlphaFoldを使ってタンパク質の構造にアクセスできるようになりました。
一方、ベイカー教授は構造予測に加え、特定の構造を形成する配列を設計するためのRosettaというプログラムを開発。AlphaFoldの登場以降はAIを導入し、構造予測とタンパク質設計の精度をさらに向上させました。
Rosettaは完全なオープンソースとして公開されており、学習にも非常に有益なプログラムです。
構造解析データとPDBの貢献
これらAIモデルの学習には、X線結晶構造解析、NMR、クライオ電子顕微鏡などによって得られた構造データが使用されており、これらはProtein Data Bank(PDB)によって提供されています。
受賞者のジャンパー博士は、Natureの記事や、C&ENの記事で、「高精度な構造を解明し、関連情報と共に無償で提供してきた構造生物学者やPDBの貢献が、この成功に欠かせなかった」とコメントしています。
蛋白質研究所は worldwide PDB の一員として PDBj を運営しており、アジア・中東地域のデータ処理を担当。
世界の全登録データの約30%を処理し、日米欧でデータを交換・統合することで、世界にひとつのPDBとして公開しています。
https://pdbj.org
研究所からのコメント
古賀 信康 教授(蛋白質研究所)より
本ノーベル賞は、David Baker, Demis Hassabis, John Jumper 博士らへ与えられましたが、個人的にはタンパク質科学がこれまでに生み出してきた知識の総体に対するノーベル賞という見方もできるように思っています。
そのため、博士らへの祝辞と共に、蛋白研を含む世界中のタンパク質科学コミュニティへも「おめでとうございます!」と述べたいと思います。
栗栖 源嗣 教授(PDBj責任者)より
自由に利活用できるOpen DataとしてPDBを整備・公開する重要性が改めて認識されました。
革新的な構造予測手法(RosettaFoldやAlphaFold)の学習データとして活用されているPDBの関係者として、ノーベル賞受賞をお祝い申し上げます。
受賞対象の業績は、実験構造生物学と融合し、タンパク質分子をより動的かつ広範に記述する新しい科学の発展を加速することでしょう。
※1 PDBjの活動は大阪大学蛋白質研究所の共同利用・共同研究拠点活動として運営され、JST-NBDC(JPMJND2205)およびAMED-BINDSの支援を受けています。