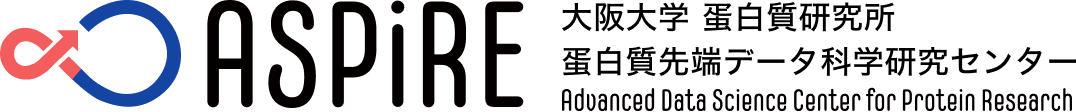Researcher
栗栖 源嗣
Genji Kurisu
- 所属:
- 大阪大学 蛋白質研究所 蛋白質構造データバンク構築研究室 教授
- 研究内容:
- 蛋白質構造データベース(PDB)などを世界と協力して作る
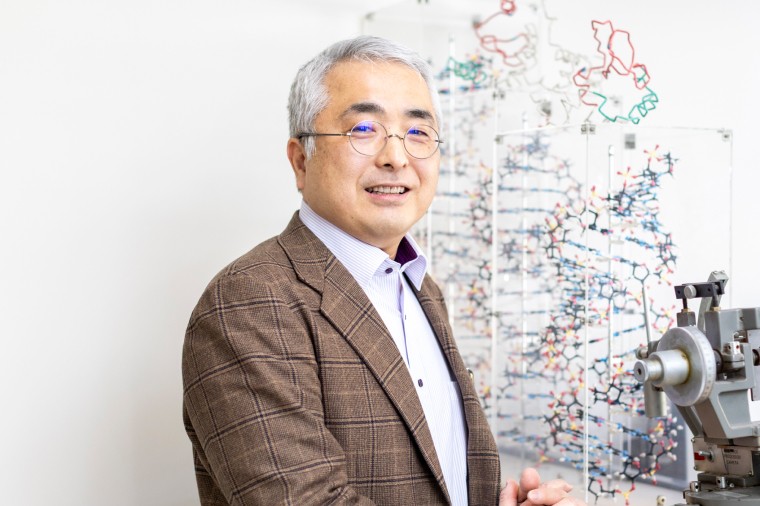
研究紹介
実験的に決定した蛋白質や核酸など生体高分子の3次元構造情報を保存する世界で一つのProtein Data Bank (PDB)を日米欧の国際連携の下で構築し,それに付随する関連データベースと一緒に20年以上に渡り大阪大学のサイトから全世界に公開しています。世界中からProtein Data Bank Japan (PDBj)として知られており,独自のツールや2次データベースの開発も行なっています。世界中で毎日200万件以上がダウンロードされ,基礎研究から創薬などの応用研究まで幅広い研究に活用されています。
もっとくわしくQ&A
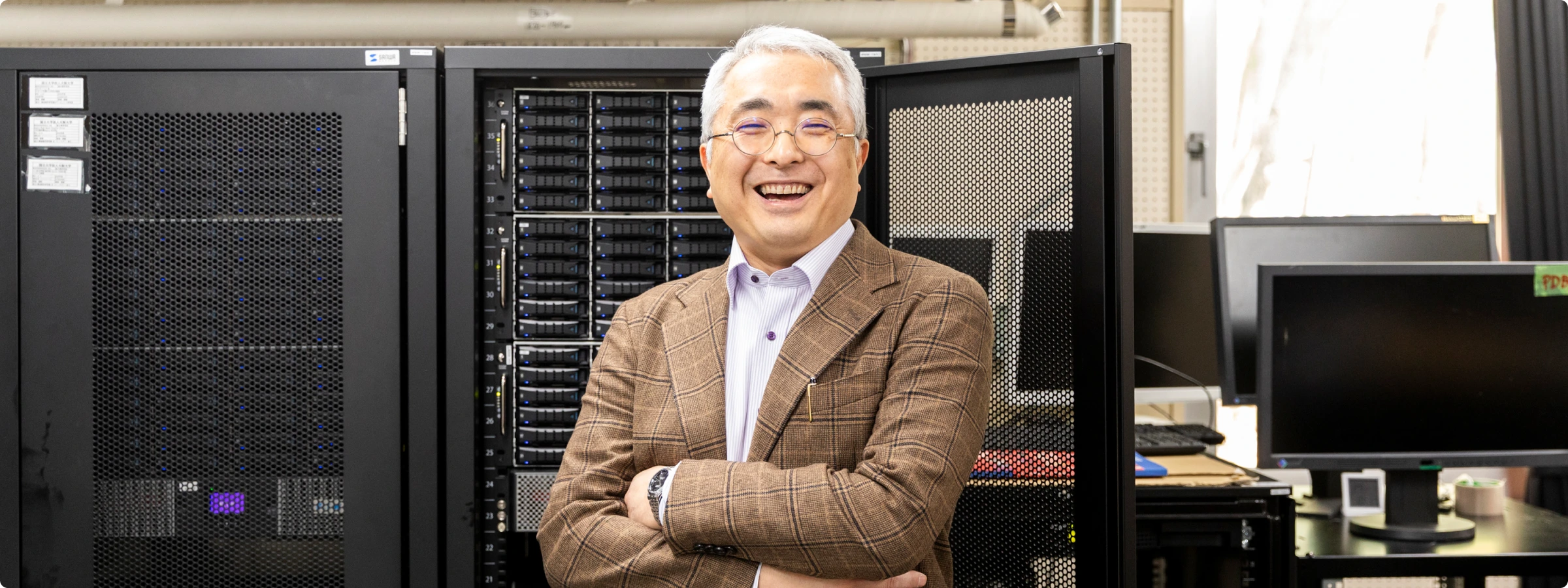
この研究のユニークな点や強みを教えてください。
実験的に決定した蛋白質や核酸などの構造情報は世界に1つのデータベースProtein Data Bank(PDB)に集積されています。PDBは生命科学分野の基盤となる国際的なデータベース Global Core Biodata Resource (GCBR)に認定されており,世界レベルのデータベースです。国際的なデータベースが大阪大学にあり,その国際基準を大阪大学で策定している点が強みです。
この研究の成果は、社会や産業にどのように役立つと考えていますか?
Protein Data Bank(PDB)は新薬開発や産業応用に欠かせない基本的な情報基盤です。ほぼすべての製薬会社がPDBのデータを利用して薬を作っています。また国際的なデータベースの拠点が国内にある利点を活かし,信頼性の高い情報を日本語でも発信することで中等・高等教育にも貢献しています。
この研究では、データサイエンスがどのように活用されていますか?
この研究はデータサイエンスを支える研究です。自由に利活用できるOpen Dataとして長年にわたりProtein Data Bank (PDB)を整備し公開することが,2024年のノーベル化学賞の受賞対象となった革新的な構造予測手法の開発(RosseTTAFoldやAlphaFold)に活かされました。ノーベル賞受賞者が,研究を実施する上でPDBのデータが極めて重要であったとコメントされています。
共同研究の事例や今後のコラボレーションの可能性について教えてください。
我々の研究室に加えて,米国ラトガース大学とカリフォルニア大学サンディエゴ校の2か所に拠点を構えるStephen K. Burley教授のチーム(RCSB PDB),NMRの実験データを収録するコネチカット大学Jeffery C. Hoch教授のグループ(BMRB),イギリスにある欧州生物情報科学研究所(EMBL-EBI)に拠点を構えるSameer VelankarおよびKyle Morrisチームリーダーのグループ(PDBe&EMDB)が共同でPDBデータの登録・維持・管理を行っています。2022年からは,中国・上海にある国立蛋白質研究施設のWenqing Xu教授のグループ(PDBc)との共同研究も開始しました。国内では,DBCLSの片山教授のグループとデータベースの統合利用に関する共同研究を行っています。
今後の研究の展望や目標を教えてください。
国際的なデータベースセンターとして日本で活動し,25年に及ぶ研究活動から国際的に広く認知されている利点を生かして,正確で使いやすい情報を英語だけでなく日本語(中国語,韓国語)でも迅速に提供していきます。また,四半世紀という節目の年を迎えて,生命科学研究を支える情報基盤を提供する研究室として,より一層の国際連携とデータ利用の統合化を進めていきたいと思っています。
主な出版物
論文
- G.-J. Bekker, C. Nagao, M. Shirota, T. Nakamura, T. Katayama, D. Kihara, et al., Protein Data Bank Japan: Improved tools for sequence-oriented analysis of protein structures, Protein Science, 34(3), e70052 (2025).
https://doi.org/10.1002/pro.70052 - The wwPDB Consortium, EMDB—the Electron Microscopy Data Bank, Nucleic Acids Research, 52(D1), D456–D465 (2024).
https://doi.org/10.1093/nar/gkad1019 - J. C. Hoch, K. Baskaran, H. Burr, J. Chin, H. R. Eghbalnia, T. Fujiwara, M. R. Gryk, T. Iwata, C. Kojima, G. Kurisu, D. Maziuk, Y. Miyanoiri, J. R. Wedell, C. Wilburn, H. Yao, M. Yokochi, Biological Magnetic Resonance Data Bank, Nucleic Acids Research, 51(D1), D368–D376 (2023).
https://doi.org/10.1093/nar/gkac1050 - S. Velankar, S. K. Burley, G. Kurisu and J. C. Hoch and J. L. Markley, The Protein Data Bank Archive, in R. J. Owens (ed.), Structural Proteomics, Methods in Molecular Biology, vol. 2305, Humana, New York, NY (2021).
https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1406-8_1 - G.-J. Bekker, M. Yokochi, H. Suzuki, Y. Ikegawa, T. Iwata, T. Kudou, et al., Protein Data Bank Japan: Celebrating our 20th anniversary during a global pandemic as the Asian hub of three dimensional macromolecular structural data, Protein Science, 31, 173–186 (2022).
https://doi.org/10.1002/pro.4211