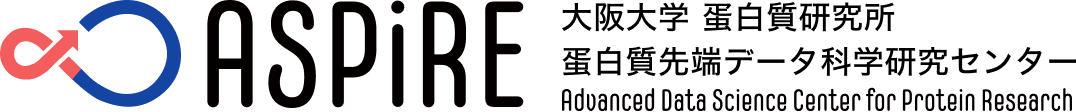Researcher
岡田 眞里子
Mariko Okada
- 所属:
- 大阪大学 蛋白質研究所 細胞システム研究室 教授
蛋白質ネットワーク研究室 教授(兼任) - 研究内容:
- 細胞内のシグナル伝達系や転写制御における蛋白質間の相互作用や蛋白質とDNAの相互作用を、数理モデルや計算手法を用いて予測・検証し、蛋白質ネットワークの動態とその細胞制御や疾患における役割を明らかにする
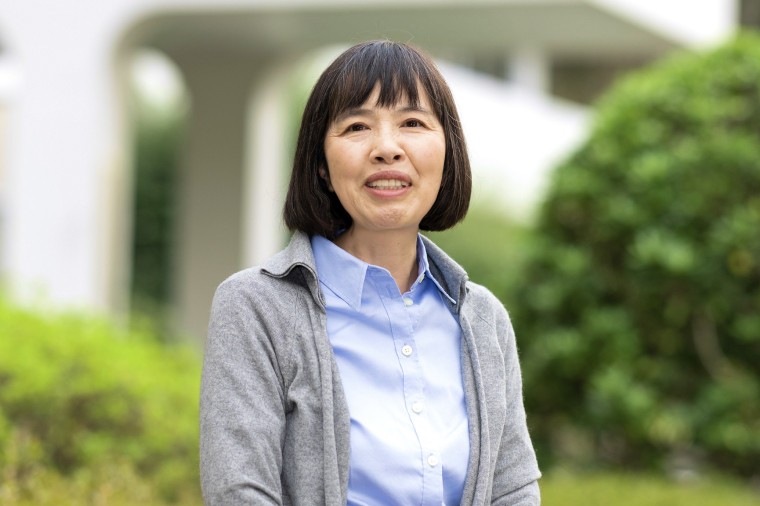
研究紹介
細胞内の複雑な情報伝達の原理解明を目指し、オミクス計測と数理モデルを組み合わせ、遺伝子の制御機構と規則性を明らかにして細胞制御に活かすことを目指しています。また、自然言語処理(NLP)や深層学習(DL)などを取り込んだ、最新の細胞モデリング手法や一細胞シーケンスデータの解析手法の開発にも取り組んでいます。
もっとくわしくQ&A
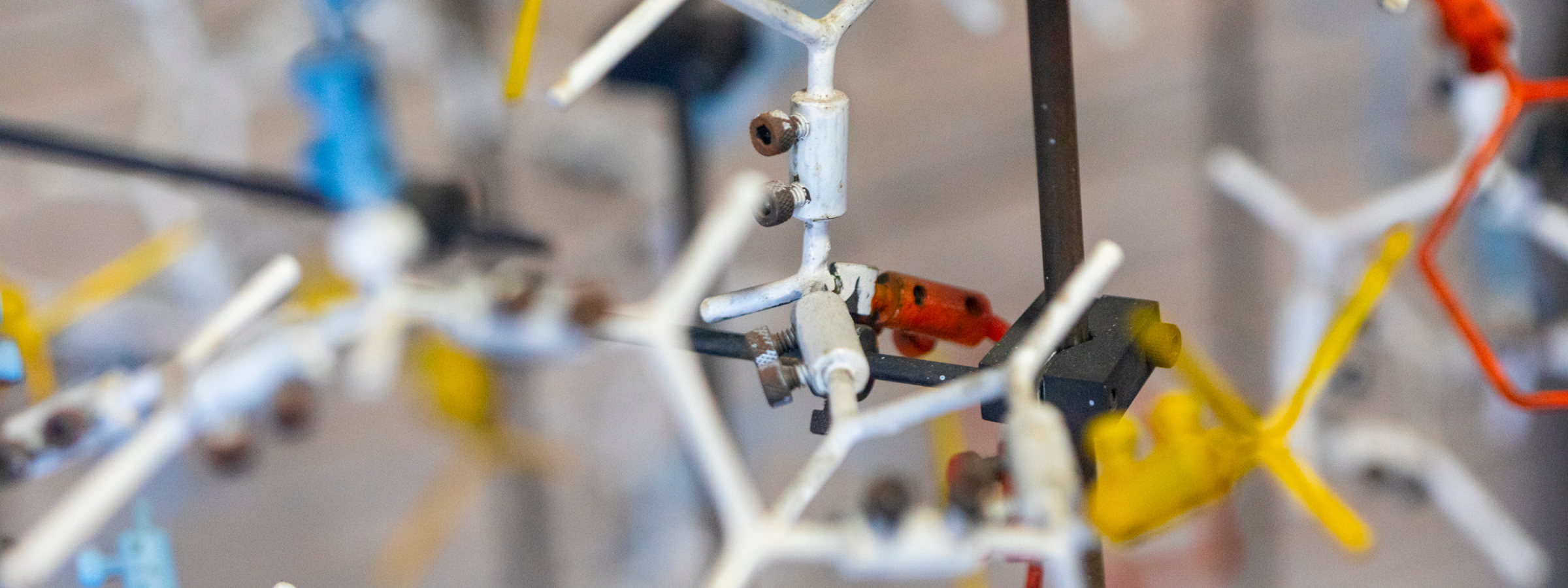
この研究のユニークな点や強みを教えてください。
実験を基礎としたウェットとドライを密接に組み合わせたデータ駆動的な大規模な数理モデリングが、当研究室のユニークかつ圧倒的な強みだと考えています。遺伝子の制御機構を詳細に記述した数理モデルは、ネットワーク同定やパラメータ探索の点で、問題点を多く指摘されますが、そのことを生物学およびデータの視点から、多くの理論/計算系の共同研究者とともに解決していく点も強みだと思っています。
この研究の成果は、社会や産業にどのように役立つと考えていますか?
構築した数理モデルそのものが、社会の共通基盤となり発展していくという点が挙げられます。また、創薬におけるターゲット同定、制御機構解明、用量応答解析に役立ちます。数理モデリングの計算ツールは、教材としても役立つと思います。
この研究では、データサイエンスがどのように活用されていますか?
数理モデル構築の過程では、自然言語処理(NLP)や大規模言語モデル(LLM)を用いた文献からの情報抽出と遺伝子ネットワークの同定、遺伝的アルゴリズムやニューラルネットワーク(NN)を用いたパラメータ同定などに、データサイエンスを用いています。また、一細胞シーケンスデータの解析や、数理モデルから得られた大量のシミュレーション結果の解析の際に、深層学習(DL)を用いています。
共同研究の事例や今後のコラボレーションの可能性について教えてください。
人工知能(AI)が発展した一方で、それがカバーできない分子メカニズムを明らかにしようとする考えが近年浸透したことにより、数理モデリングに一層の注目が集まっているように感じます。ここ数年は、製薬企業からの社会人博士課程学生の受け入れを行なっており、このうちの1名は昨年博士課程を修了し、新規の皮膚老化マーカーの同定とその阻害物質の機構を明らかにすることができました。
また、Quantitative Systems Pharmacology(QSP)におけるライフサイエンス系の数理モデルに注目が集まっており、その流れにおいても、共同研究の機会が増えているように思います。
今後の研究の展望や目標を教えてください。
これまで個別に構築してきたシグナル伝達系の数理モデルを統合することで、薬剤の応答性や副作用を網羅的に予測できるモデルを構築したいと考えています。これは、数理モデリング研究を始めた20年以上前からの夢です。また、蛋白質の立体構造解析では難しかったシグナル伝達系の蛋白質相互作用を、分子動力学シミュレーションと細胞シミュレーションを組み合わせて解析し、遺伝子変異の情報が細胞ネットワーク全体にどのように伝達されるかを明らかにすることにも興味があります。非常に挑戦的なテーマですが、さまざまな研究者との共同研究によって現在進行中です。
主な論文、書籍
論文
- K. Arakane, H. Imoto, F. Ormersbach and M. Okada, Extending BioMASS to construct mathematical models from external knowledge, Bioinformatics Advances, 4(1), vbae042 (2024).
https://doi.org/10.1093/bioadv/vbae042 - H. Imoto, S. Yamashiro and M. Okada, A text-based computational framework for patient-specific modeling for classification of cancers, iScience, 103944 (2022).
https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.103944 - H. Michida, H. Imoto, H. Shinohara, N. Yumoto, M. Seki, M. Umeda, T. Hayashi, I. Nikaido, T. Kasukawa, Y. Suzuki and M. Okada-Hatakeyama, The number of transcription factors at an enhancer determines switch-like gene expression, Cell Reports, 31(9), 107724 (2020).
https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.107724 - H. Shinohara, M. Behar, K. Inoue, M. Hiroshima, T. Yasuda, T. Nagashima, S. Kimura, H. Sanjo, S. Maeda, N. Yumoto, S. Ki, S. Akira, Y. Sako, A. Hoffmann, T. Kurosaki and M. Okada-Hatakeyama, Positive feedback within a kinase signaling complex functions as a switch mechanism for NF-κB activation, Science, 344(6185), 760-764 (2014).
https://doi.org/10.1126/science.1250020 - T. Nakakuki, M. R. Birtwistle, Y. Saeki, N. Yumoto, K. Ide, T. Nagashima, L. Brusch, B. A. Ogunnaike, M. Okada-Hatakeyama* and B. N. Kholodenko*, Ligand-specific c-Fos expression emerges from the spatiotemporal control of ErbB network dynamics, Cell, 141(5), 884-896 (2010).
https://doi.org/10.1016/j.cell.2010.03.054 *Corresponding authors.